「ロゴタイプのサンプル1,000例、見てみませんか?号」 |
 |
「やまさん」こと、おちゃのこ山崎です。
7月前半だというのに、もう酷暑日が続き、この調子だと8月はどんなことになるのか心配です。
あまりにも暑いと、いくらエアコンを運転していても仕事に身が入らない気がしますね。もしエアコンが故障したらどうしようと、いらぬ心配をしてしまいます。
こんな時には文字ばかりの本はあまり頭に入らないので、オススメ参考書もビジュアル中心の本を選んでみました。
今回ご紹介するのは、当代第一線のデザイナーの作品ばかりを1,000点もオールカラーで掲載したロゴタイプの見本帳です。
涼しいお部屋でパラパラめくり、ご商売のロゴタイプをリニューアルするときの参考にしてください。
おちゃのこ最新ニュース
|
今週のトピックス
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お知らせ 大好評!カート離脱フォローのご紹介
|
皆さん、こんにちは。 今回は、大変好評いただいているカート離脱フォローのご紹介です。
|
オススメ参考書~読んだら即実践してみよう!
|
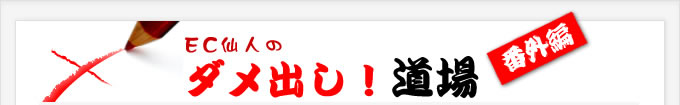
おちゃのこネットの特徴は? とスタッフさんやベテラン店舗さんに ・低コストでオンラインショップが開ける このように山ほどの強みや特長、機能などが挙げられるでしょう。
でも… 今さらすぎて、当たり前すぎて、おちゃのこスタッフさん達ですら挙げていない基本中の基本の特徴があります! それは…(もったいつけるな~(^^;)) 「ネット上に自分のお店が持てる」 ということです! なんじゃそれ!? 当たり前やん! と怒らないでください(^^;) 「ネット販売」とか「eコマース」とか言いますが、これって別に店を持つことではないですよね。 メルカリやヤフオクみたいなフリマに「出品」して匿名やニックネームでただ物を売る方法だってありますし、一般的になっています。 Amazonのような巨大マーケットで販売するのも「店を構える」のとは少し違います。お客さんは物を買っているけど、Amazonの何という出品者から買ったかなんて関心はほとんどないし、すぐ忘れる。 楽天市場は一応「出店」という形はとっていますが、あくまでドメインは rakuten,co,jp/xxxxx/ というテナント扱いですし、お店はお客様(購入者)のメールアドレスさえ得ることができず、退店すれば顧客との縁も切れる。かなり高い販売の手数料も取られる。 おちゃのこネットは、本来のオンラインショップ、ネットショップのように独自のドメインで、プロバイダーのレンタルサーバーやホームページ開設よりもうんと安いコストで「自分のお店=拠点」を構えることができるのです。 お客様に対しても、「ウチはこういうお店で、こんな店長が運営しています!」 いつ消えてしまうかわからないモールやフリマの出品者とは安心感も信頼度もまったく違います! いつでも連絡や質問やリピート注文も、継続取引もできますよ! 1回限りの売り逃げ業者とは違いますよ! ということもアピールできるのです。 お店にとっても、個々のお客様とのコミュニケーションやお取引履歴、お客様の個人情報までしっかりと入手・管理できる(今後の提案や連絡も可能)わけですから、モール出店やフリマ出品とは差別化が可能なのです。 でも、このおちゃのこ出店の基本中の基本の特徴をあまり理解せず、活かしきれていないお店が多く、もったいなく感じます。 もう一度言います。 「おちゃのこネットでeコマースをやる意味」 は、 「ネット上に自分のお店が持てる」 ということです。 大昔の商売で言えば、行商人でも露天商でもなく、ちゃんと表通りに店を構え、信頼される商いを行えるということ。 裏を返せば、おちゃのこネットは信頼されるお店だからこその商品やサービスを売るのに向いているECの手段だということです。(一時でさっと売り逃げするようなお店、商品には向いてない!) どこで買っても同じ、ただ安いところで買えばいい商品なら、みんなamazonやメルカリやアジア系格安モールでの一見買いになってしまいます。 でも、商品にちゃんと作り手の物語やメッセージがあって、物のスペックと価格だけでなく、こだわりや思い入れ、提案やアイデア、使用感、アフターサービスなど「物以外」の付加部分の価値が高い商売をしているのなら、おちゃのこネットに自分のお店を持って商売する意味・意義がある! と言えるのです。 それは言い換えるなら、「物を売る=商売」としているお店ではなく、「お得意様を作り育てる=商売」として志し、継続しているお店だと言えるでしょう。 ただただ、目先の流行りものや粗悪品を安く仕入れ、「在庫限り!」「限定〇〇〇個!」「今だけ〇% off!」のような悪いマーケティングテクニックだけで薄利多売するような方は、おちゃのこネットではなくamazonやフリマ出品で目先の売上を狙って疲弊・消耗しながら薄利の安売り合戦を頑張ってください。(皮肉) そうではなく、こだわったり思い入れのある良い商品やサービスをを企画・開発し、お客様も大切にできるお店は、ぜひおちゃのこネットでその特徴を活かして頑張ってください。(応援&賞賛) ただし、ネットの上で人の集まる場所はSNSです。 検索→お店 の流れは ごくわずかな目的意識の明確なお客様だけです。SNSで商品やお店を知る→お店 の流れを作らないと集客がなかなかうまくできません。 少しだけマーケティング的なことを言うと、現代の「消費行動」はスマホを起点に発生しており、空き時間にスマホをいじっている(その多くは動画サイトを含むSNSを見ている)際に何らかの商品を知り、瞬間的に買いたい衝動にかられ、商品を売っているお店にアクセスし、買い物行為を完了させる「パルス型消費行動」が広まっているそうです。(Google日本の調査報告) この「パルス型消費行動」の特徴は、最初から特定の商品を購入する意図を持たず、ネット上の活動で出会った新情報が脳内にある既存情報や潜在欲求と結びついた瞬間に、それまで自覚、想定していなかった購買行動を起こしてしまうことで、従来の街の店で目にした商品を「衝動買い」することとは異なるようです。 例1)なんとなく目の疲れや視力減退を感じていた人が、今まで知らなかった目に良い新成分をたまたま眼科医のSNSで知ったことで、その成分が高濃度に含まれるサプリを検索して買ってしまった。 例2)漠然と、ダイエットやスタイル維持のために運動しなきゃなー! と思っていた人が、インフルエンサーがSNSで紹介していたトレーニングマシンを見て衝動的に検索したが、高すぎたので安価な類似品を見つけて購入してしまった。 例3)お菓子作りが好きな彼女のいる旅行好きな自分、SNSで見かけた京都の老舗和菓子店の「和菓子作り体験教室」に行くために、急遽彼女の休みの予定を確認して京都旅行を計画! などなど、いずれも商品そのものを見ての衝動買いではなく、スマホ起点、SNS起点で2つ以上の情報が結び付き「欲しい物」が生じて購買行動が衝動的に発生している点、販売者が想定できない、していないことがきっかけで購入が起きてしまう点が特徴的です。 一方で、昔からマーケティングの世界で想定される消費行動を「ジャーニー型」とか「カスタマージャーニー」と呼びます。 パルス型消費が広まったとはいえ、ジャーニー型が廃れたりなくなったわけでは決してありません。パルス型に多い安価で瞬間的に購入決定しやすい消費財などに対して、ジャーニー型に多い耐久財や高級品、オーダーメイド品は認知してから購入までに期間を要することも多く、顧客は徐々に情報や知識を得ながら比較選択し購入に至るので、お店側も顧客の意思決定までに関与する時間や機会が充分にあると言えます。 わかりやすく言えば、接客・Q&Aでお客様の心理変化に影響を与えられる! ということです。 専門店として「おちゃのこネット」に店を持ち、SNSでお客様と出会い、コミュニケーションし、ジャーニーに影響を与え、購入決定に誘導する。 正にフットワーク軽く商品ページ登録制作でき、お客様に個々に接客でき、信頼を得やすいおちゃのこネットにお店を持つ意義だと言えるのではないでしょうか! 店長・店主の皆様、今一度おちゃのこネットに拠点となるお店を持っている意義・意味を初心に返って見直してみてください。 集客に広告費をふんだんに使える大手さんなら、新規の一見客を集め続けられるかも知れませんが、広告費の限られるスモールショップは、リピートと客単価の高い優良顧客を着実に1人ずつ獲得・育成することが有効です。 それがやがてお店の財産となるはずです。 一方でSNSで商品そのもの以外の情報や用途提案などを発信しながらパルス型消費と新規客獲得も拾っていく。現代型オンラインショップのサバイバル戦術だと思います。 以上。ダメ出し!道場でした! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国際紛争や情勢不安、自然災害などによる円安物価高、資源高、エネルギーコスト高などで逆風の強い時代ですが… マイナスムードに負けず、「ピンチはチャンス!」と思い、新しいアイデアと新商品、新サービスを開発して乗り越えましょう! 差別化するアイデア出し、商品企画、ジリ貧回避、マンネリ化打破などアイデアに行き詰まった際はぜひお気軽にご相談ください! きっとヒントを見つけられます!  毎回「ダメ出し!道場」登場のお店に電話でインタビューをさせていただいていますが、軽くインタビューと言いながら、実際には事前にお店のサイトを1~2時間かけてじっくり拝見し、お客様目線、プロ目線の両方から疑問点、気づいた点を洗い出してからお電話させていただいています。 最初はこちらからいろいろとご質問をさせていただき(インタビュー)ますが、後半はお店からのご質問、ご相談を受け、回答やアドバイス、アイデア、事例紹介など(プチコンサルティング)させていただいています。過去平均すると1店舗様に1時間半~2時間程度はかけています。 そのためか、インタビューさせていただいたお店の方々からは、下記のような感謝や喜びのお言葉を多くいただいています! ◆「目からウロコが落ちた! たくさん気づきがあった!」 ◆「自身が気づいていなかった強みや特徴を見つけてもらった!」 ◆「ただのインタビューかと思ったら、こんなにヒントやアドバイスを貰えるなんて思わなかった! ありがとうございました!」 ◆「新商品のアイデアまで出してもらえるとは! ワクワクしました!」 ◆「課題がハッキリと浮き彫りになり、やるべきことが整理できた!」 ◆「問題はホームページだけじゃないってことが、嫌というほどわかった!」 そこで、「ダメ出し!道場」に登場するのはちょっと勇気がないけれど、太田の電話インタビュー&プチコンサル は受けてみたい! というお店のために、有償でお受けしたいと思います! 通常 個別相談会:2万5000円のところ、メルマガ購読者限定で 先着順にて受付させていただきます。(週に2店舗程度・状況に応じて) 下記内容をご記入の上で太田まで直接メールください。 内容: 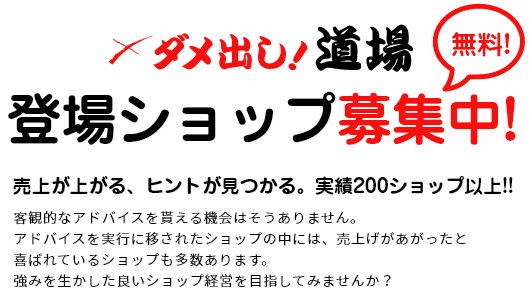 さて… |
このコーナーでは、テンプレートのカスタマイズについて、実際のサンプルページを元に紹介していきます。

皆さん、こんにちは。おちゃのこネットの刑部です。
今回のデザイン道場は、商品一覧や商品詳細ページの販売価格の通貨ラベルと税表示の文字サイズを小さくする方法をご紹介します。
 |
デザイン管理→スタイルシートの編集から下記の指定をコピーして貼り付けてください。
.responsive .tax_label,
.responsive .currency_label.before_price,
.responsive .currency_label.after_price {
font-size: 85%;
}
.responsive .detail_page_body .tax_label,
.responsive .detail_page_body .currency_label.before_price,
.responsive .detail_page_body .currency_label.after_price {
font-size: 77%;
}
.responsive .currency_label {
font-size: 77%;
}
なお、お問い合わせは下記ページからお願い致します。
編集後記
|
■おちゃのこネットのご利用方法については、よくあるご質問も参照ください。(https://www.ocnk.net/faq/) ■おちゃのこネット公式ブログ ■おちゃのこネットFacebook ■おちゃのこネット公式twitter ■ネットショップにお役立ち。弊社は下記のサービスも提供しています。 ■受信の停止は、最末尾のURLをクリックしてください。 ■個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。(https://www.ocnk.net/company/privacy.php) |
Copyright (C) 2004-2024 OCHANOKO-NET All Rights Reserved.





