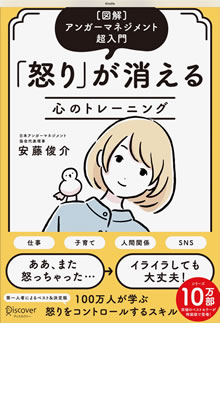「怒りをコントロールする『アンガーマネジメント』とは?号」 |
 |
「やまさん」こと、おちゃのこ山崎です。
都合により配信が1日遅れました。申し訳ありません。
ひょっとすると関東は梅雨入りなしに夏になるのでは? と思われた今年の天気ですが、2週間遅れで梅雨入りとなり、なんとか日本の四季は保たれたようです。
そして東京は都知事選挙に突入しました。法の抜け穴を突いたパフォーマンスが話題になったりして、本来の選挙戦とは違うところに注目が集まっていますが、これもSNS社会の副産物なのでしょうか。
SNS社会といえば、ネット上でのやり取りで腹を立てる人が多くなっているそうです。大勢の人たちとのコミュニケーションが増えたせいで、思わずきつい言葉を投げつけてしまったり、相手の立場を考えない対応をしてしまったりする状況が発生しやすくなっているのでしょう。
「怒りっぽい」のは社会人の大人としてはマイナスの要素ととられがちです。道路上でカッとなってしまうあおり運転は犯罪ですが、ビジネスの現場でも怒って得をすることはありません。
今回の「オススメ参考書」は怒りをコントロールするアンガーマネジメントの本を取り上げることにします。
おちゃのこ最新ニュース
|
今週のトピックス |
||||||||||||||||||
お知らせ おちゃのこネット20周年
|
2024年6月21日、おちゃのこネットは20周年を迎えました。 2004年のサービス開始以来、延べ10万ショップの方にご利用いただきました。 まだまだ、皆さんに満足していただけるサービスにはなっていないと思います。 今後ともよろしくお願いいたします。
|
オススメ参考書~読んだら即実践してみよう!
|
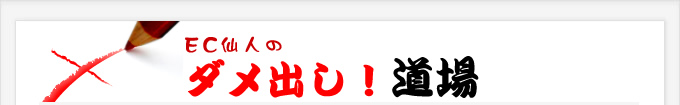
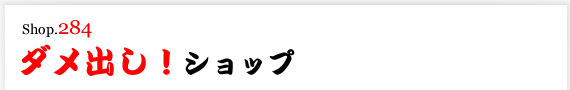
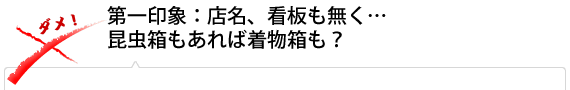 トップページ、最上部の「昆虫館・博物館・全国の昆虫愛好家様への納品実績が品質を証明します」と中央の横スクロールのバナー画像から、なんとなく昆虫を飾る箱の専門店さんかなー? 程度には見えるのですが… 店舗名やメインキャッチコピーの入った看板画像もないので、どこのどんな店主や会社がやっているお店なのかがイマイチ伝わってきません。(メーカーなのか小売店なのかもわからない…) 後ほどのインタビューでお聞きした会社の強みや特長のほんの一部しか、ファーストビューでは感じられず、今一度、初見のお客様にまずは何を伝えたいのか? 知って欲しいのか? を整理して掲載して欲しいところです。 私は、看板もないことから、自社サイトの「カート機能」と割り切っておちゃのこネットを使っているのかな、と見えました。 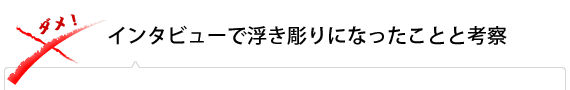 ティーウッドさんは岡山県の中央部、久米郡美咲町にあり、昭和48年(1973年)創業の高橋木工という家具製作の会社が前身で、今でもオーダーメイドの作り込み家具の事業を中心に、住宅リフォームやキャンピングカーの居室(キャンパーシェル)の製作などもなさっています。 昭和55年からは、昆虫関連商品を扱う大手問屋さんとのご縁で、通称「ドイツ箱」と呼ばれる昆虫標本箱を製造卸売りするメーカーとしても事業展開され、現在では昆虫標本コレクターの間では誰もが知る一流メーカーさんのようです。 「ドイツ箱」はドイツ式の昆虫標本箱というのが元のようですが、標本は1年、2年などの短期間ではなく、何十年もの保管・展示が求められるため、湿気、害虫やカビ、ホコリなどの侵入を防ぐ気密性、精密性と内部の湿度を一定に保つ性能が求められるそうです。 世界的に見ても、四季の寒暖差があり、湿度が高く、標本がカビたり、標本を食べてしまう害虫の侵入のリスクも高い日本の気候・環境においては、ドイツ・ヨーロッパなど乾燥した環境よりもより気密性や湿度を保つ性能の高い標本箱が求められ、日本の標本箱のクオリティは世界でもトップクラスの品質だそうで、海外からも高い評価を受けて買い求められているそうです。 店長の高橋利枝さんは現社長の娘さんで、創業者のお孫さん。 見方を変えれば、ティーウッドさんは木工の職人でもある社長(お父様)と職人仲間の技術を中心に成り立っている会社で、マーケティングや新規営業は得意ではない「モノ作り」の会社。 職人・技術者ならではの社長のコダワリや頑固さとぶつかり合いながらも、ティーウッドの持つ強みや特長を生かした商品・サービスを岡山の地から全国~世界へと発信しようと日々お忙しく頑張っておられる利枝店長さんです。 ネットではおちゃのこショップの他に その他東京ギフトショーや大阪ギフトショーへの出展など、リアルでの市場開拓や、現在は新商品の「ランドセルチェア」を広めようと地方イベントへの出店やクラウドファンディングなども計画中だとか。 ------------------------------ メーカーとしての電子カタログ的な位置づけなのか… 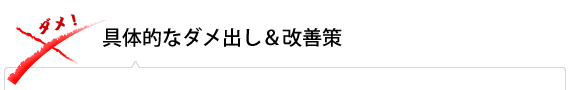 主力のドイツ型標本箱ですが、K型・N型・T型などいくつかの種類があったり、サイズも塗装も何種類かあるようですが… 商品カテゴリーの一覧を見ても、種類、塗り、個数、UVフィルム貼りなどいろいろな要素の違いのあるものがごっちゃに一覧されているために、初心者には違いや特長の差がなかなかわかりません。 K型・N型・T型とは? 何が違う? などの説明も見当たりません。 まずは、型の違い、大きさの違い、塗りの違い、その他機能や仕様の違いなど、分類や種類の違いと特徴と価格が一覧できる表をフリーページで作って、そこから各商品ページに誘導するようなナビゲーション(店内導線)を作られるのが良いかと思います。 特殊標本箱は別カテゴリーにされていますが… 初心者、初めての方でもわかるように! を意識して分類してみてください。 ------------------------------ 全体としてまず「A:昆虫標本用の商品」と「B:それ以外の商品」をそれぞれの下に A:昆虫標本用ドイツ箱、収納庫、飾り棚、収納棚 のように分類すると、木製品メーカーとして昆虫関連とそれ以外も製造販売している点が分かりやすく伝わると思います。 また今後、ランドセルチェアやその他家具製品、キャンパーシェルなどを掲載・販売されても、違和感なくわかりやすいと思います。 ------------------------------ 既にティーウッドのドイツ箱を持っている人には今の写真で分かっても、実物を見たことのない、触ったことのない人には今の写真だけで数万円もする買い物の決断はなかなかできません。 通販では写真は命です。妥協せず高画質な物を掲載しましょう。 できることならば、艶感や質感、ガラスなどの光沢感を感じさせるように数秒でも構いませんので動画でクルっと回しながら角度を変えて見せるような工夫もあるとなお良いでしょう。 ------------------------------ ティーウッドさんの会社もブランドも知らない方、知ったばかりの初心者さん向けに、「私たちティーウッドとは」のような自己紹介コンテンツもぜひ用意して欲しいです。どこの、どんな会社でどんな経営者やスタッフ達で何をしているのか?(どんな工場でどんな風にモノ作りしているのかなど) 製造業、メーカーさんには個人への販売や商談はお断りというところも多いですので、歓迎ならば明記しておきましょう。 またその逆で「オンラインショップは個人向け」と思い込んで見てしまったり、メーカー直営とは思わず単なる小売店に見えていると、法人のバイヤーや商品企画担当者からの相談が来にくいことになっていたりします。 また、「マスコミ、メディアの方、取材歓迎」なども書いておくと、取材や相談を受けやすくなります。 気難しい敷居の高い職人系メーカーと思われない、どんなことでも相談しやすいメーカー という印象を意識して発信しましょう。 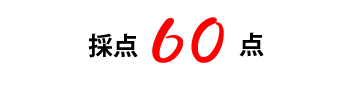 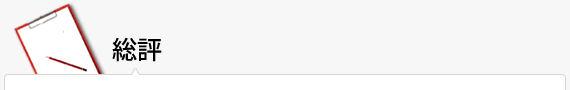 ティーウッドさんの「昆虫標本箱」における品質や実績は「一流」だと思います。メーカーとして商品の種類や違い、特徴を分かりやすく整理して掲載することを今一度見直しましょう。 それを軸にしつつ、商品そのものだけでなく、「ティーウッドは何ができる会社なのか?」という本質を今一度社内でブレストしてリストアップし、1枚にまとめたページをしっかりと作り込んでいかれると、「単にカートで標本箱が売れる」だけではないいろいろなビジネスチャンスが広がっていくと思います。 オンラインショップサイトにおいても、単なる小売店ではない「モノ作りできるメーカーさん直営ショップ」は、お客さまや市場からの問い合わせや意見を吸い上げて、今後の商品やビジネスに生かすことができるのでとても有利です。 自社サイト、SNSとおちゃのこ店をぜひうまく組み合わせて、トータルでのビジネスの向上に生かしてください。 利枝店長お一人でのネット活動は孤独で労力的にも大変だと思いますが、うまく社内を巻き込んで、啓蒙しながら頑張ってください。 相談役(応援団)が必要な際はお気軽にお声がけください(^^;) ------------------------------ ティーウッドさんの標本箱の精密さや保存性の高さを示すような実験やデモを撮影して発信するなど、技術力アピールももっともっとできるでしょう。 新たな活路を見出す大きな武器となるはずです。 余裕があれば、X、Facebook、Youtube にも投稿していきましょう。 ------------------------------ 以上。「ダメ出し!道場」でした! ────────────────────────────── 国際紛争や情勢不安による円安物価高、資源高、エネルギーコスト高などで逆風の強い時代ですが、マイナスムードに負けず、「ピンチはチャンス!」と思い、新しいアイデアと新商品、新サービスを開発して乗り越えましょう! 差別化するアイデア出し、商品企画、ジリ貧回避、マンネリ化打破など、アイデアに行き詰まった際はぜひお気軽にご相談ください!  毎回「ダメ出し!道場」登場のお店に電話でインタビューをさせていただいていますが、軽くインタビューと言いながら、実際には事前にお店のサイトを1~2時間かけてじっくり拝見し、お客様目線、プロ目線の両方から疑問点、気づいた点を洗い出してからお電話させていただいています。 最初はこちらからいろいろとご質問をさせていただき(インタビュー)ますが、後半はお店からのご質問、ご相談を受け、回答やアドバイス、アイデア、事例紹介など(プチコンサルティング)させていただいています。過去平均すると1店舗様に1時間半~2時間程度はかけています。 そのためか、インタビューさせていただいたお店の方々からは、下記のような感謝や喜びのお言葉を多くいただいています! ◆「目からウロコが落ちた! たくさん気づきがあった!」 ◆「自身が気づいていなかった強みや特徴を見つけてもらった!」 ◆「ただのインタビューかと思ったら、こんなにヒントやアドバイスを貰えるなんて思わなかった! ありがとうございました!」 ◆「新商品のアイデアまで出してもらえるとは! ワクワクしました!」 ◆「課題がハッキリと浮き彫りになり、やるべきことが整理できた!」 ◆「問題はホームページだけじゃないってことが、嫌というほどわかった!」 そこで、「ダメ出し!道場」に登場するのはちょっと勇気がないけれど、太田の電話インタビュー&プチコンサル は受けてみたい! というお店のために、有償でお受けしたいと思います! 通常 個別相談会:2万5000円のところ、メルマガ購読者限定で 先着順にて受付させていただきます。(週に2店舗程度・状況に応じて) 下記内容をご記入の上で太田まで直接メールください。 内容: 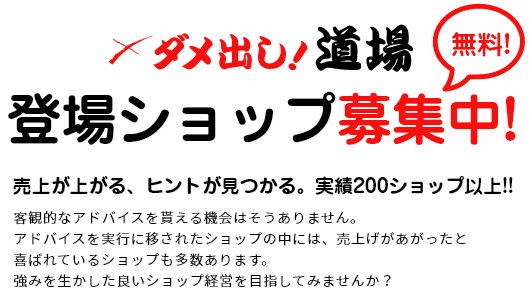 さて… |
このコーナーでは、テンプレートのカスタマイズについて、実際のサンプルページを元に紹介していきます。

皆さん、こんにちは。おちゃのこネットの刑部です。
今回のデザイン道場は、商品詳細ページのメイン画像下に表示されるサムネイル画像をスクロール表示する方法をご紹介します。
 |
デザイン管理→スタイルシートの編集から下記の指定をコピーして貼り付けてください。
.responsive .itemdetail .thumbnail {
width: 100%;
overflow-x: scroll;
scrollbar-color: #E0DFE3 #FFFFFF;
scrollbar-width: thin;
}
.responsive .itemdetail .thumbnail > ul {
width: max-content;
}
@media screen and (min-width: 500px) {
.responsive .itemdetail .thumbnail {
overflow-x: visible;
}
.responsive .itemdetail .thumbnail > ul {
width: auto;
}
}
なお、お問い合わせは下記ページからお願い致します。
編集後記
|
■おちゃのこネットのご利用方法については、よくあるご質問も参照ください。(https://www.ocnk.net/faq/) ■おちゃのこネット公式ブログ ■おちゃのこネットFacebook ■おちゃのこネット公式twitter ■ネットショップにお役立ち。弊社は下記のサービスも提供しています。 ■受信の停止は、最末尾のURLをクリックしてください。 ■個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。(https://www.ocnk.net/company/privacy.php) |
Copyright (C) 2004-2024 OCHANOKO-NET All Rights Reserved.