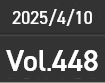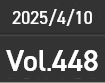購入した本の最終ページにある「奥付」まで見る人はあまり多くはないと思いますが、本書の奥付を見た人は、「福岡県糸島市」という発行元の住所を見て驚くかもしれません。
ネット全盛の現在でも、出版社のほとんどが東京の神田周辺にあり、その他の地域でも大都市にあるのが普通です。それが聞き慣れない市にあるというと興味が湧いてきます。
福岡県糸島市は福岡県最西部に位置する市で、玄界灘と背振山脈に面しています。合併によって生まれた市ですが、市名は合併前の郡名を継承しており、その名前は律令時代の郡名である怡土(いと)郡と志摩郡に由来しています。
怡土は「魏志倭人伝」に登場する伊都国ではないかと、また市内の平原遺跡は天照大神の墓ではないかとする説があるくらい、日本の古代史に関連の深いエリアです。
匠書房は本書が4冊目の刊行で、プロデュースを「うける」「まなぶ」がメインの会社です。創業者は川原卓巳氏で、全世界で1,300万部を売った『人生がときめく片づけの魔法』の著者・近藤麻理恵氏をプロデュースした人物として、また近藤さんの夫君として知られます。
したがって同社の過去3タイトルの出版物は川原氏と近藤氏の著作で、本書はこの夫婦以外の初の著作となります。
本書の著者である菅原健一氏は経営アドバイザー。株式会社ムーンショットの代表取締役CEOで、「企業を10倍成長させるアドバイザー」として、年間でクライアント10社、エンジェル投資先20社のプロジェクトを並行して進めています。著書に『小さく分けて考える「悩む時間」と「無駄な頑張り」を80%減らす分解思考』(SBクリエイティブ刊)があります。
前置きが長くなったので、いきなり目次から紹介しましょう。
・はじめに
・第1章 厚利少売で必要な「4つの基本原則」
1 提供する価値に責任をもつ
2 供給量をしぼる
3 「売上脳」ではなく「利益脳」
4 異常値になる
・第2章 付加価値の前に「本質価値」を見極める
「付加価値」は仮面をかぶっている
「新たな本質価値」を見つける方法
なぜ、ミシュランは「ガイドブック」を出したのか?
「ブランド」をつくる4つのヒント
チームマネジメントにおいても「本質価値」の見極めが大切
・第3章 「成功」から逆算して価格を決める
「目標の年間利益」を決める
「価格」は小さく分けて考える
よくある「値付けの間違い」3選
増え続ける「シン富裕層」の実態
「高い」と言われたら、どう言い返す?
・第4章 価格の壁を乗り越える「需要」の見つけ方
「需要の見極め」を制するものがビジネスを制す
需要を見極める4ステップ①お客さんの解像度を上げる
考えてみよう! 高級マッサージ店の顧客はどこにいる
需要を見極める4ステップ②候補を見つけ、さらに解像度を上げる
需要を見極める4ステップ③勇気を出して提供してみる
需要を見極める4ステップ④「相手の変化量」を聞く
お客さんは「選ぶもの」でもある
・第5章 需要を広げ、供給量を予測する「発信」の技法
「発信」には2つの役割がある
「発信」で絶対知っておくべきこと
「アカウント名」と「プロフィール」で損をしないための注意点
「なにものでもない人」でも勝機はある
ゴールは「自己紹介」ではなく「他己紹介」
・第6章 厚利少売を実現する「アクションプラン」
自分をサブキャラ扱いせず、「主人公型・脚本家」になりきる
一か八かでやる必要はない。小さく始めて、小さく拡大する
アクションプランの具体例①「会社員、副業デザイナー(35歳)」の場合
アクションプランの具体例②「無職、学歴・職歴なし(20代)」の場合
アクションプランの具体例③「地方にある伝統メーカーの2代目社長(45歳)」の場合
アクションプランの具体例④「個人事業主、ダイエットコーチ(40歳)」の場合
「利益を上げる=努力する」ではない
1年後のあなたは別人
・第7章 厚利少売を実現したあとの「持続的な成長」
哲学は変えず、変化に適応する
小さい夢をもつな。自分の可能性を信じよう
そこに「笑顔」はあるか?
・おわりに
・参考書籍 厚利少売をめざす人は、ご一読をおすすめします。
では巻頭に戻って、「はじめに」から見ていきましょう。
いきなり著者から12の質問が投げかけられます。1分以内で答えてください。
□価格を下げて競合他社に勝とうとしている
□利益よりも、まずは売上を優先しがちだ
□自分の製品はどんな人にも買ってほしい
□売っても売ってもまた仕入れたり広告を出したりで、利益が残らない
□「お客さんの数は多ければ多いほどいい」と考えている
□お客さんに感謝されることが少ない
□製品やサービスを幅広く提供していて、特定のターゲットに特化していない
□大量の在庫を抱え、在庫管理に頭を悩ませている
□いろいろな企業と価格競争をしている
□どんな人にも買ってほしいから、当たり障りない製品を作っている
□常に新しい顧客を獲得しようとしている
□集客を広告に依存している
いくつチェックがつきましたか?
「半分以下だから合格だろう」と思いましたか?
著者によれば、1つでもチェックがついた人は「薄利多売」の考え方に陥っているそうです。
多くのビジネスマンは「薄利多売」に良いイメージを持っていません。にもかかわらず、日本人はつい薄利多売に陥りがちなのだそうです。著者によれば、意識して軌道修正をしないかぎり、知らず知らずのうちに薄利多売のビジネスを続けてしまうのが日本人の特性だといいます。
次のページでは、「薄利多売」のビジネスとその反対語であり本書のタイトルでもある「厚利少売」のビジネスを表にして比較してあります。
まず「価格」について。「薄利多売」は多くの顧客を獲得するために低価格政策をとります。それに対して「厚利少売」は高価値を感じる顧客に向けた高価格政策です。
次に「利益率」。「薄利多売」は低い利益率のため多くの販売量が必要ですが、「厚利少売」は高い利益率のため少ない販売量で充分な売上・利益が得られます。
続いて「減価率」ですが、「薄利多売」は単価が低いために減価率が高くなります。それに対して「厚利少売」は高い単価なので減価率が低くなります。
「顧客」の面では、「薄利多売」は安さを求める広範囲の顧客で、リピーターは多くありません。対して「厚利少売」は高価値を求める少数の顧客が相手で、リピーターが多くなります。
「製品開発」においては、「薄利多売」は市場調査で大量生産を重視し、コスト効率を考えた製品開発になりがちです。一方、「厚利少売」は顧客の声を重視した独自性と高価値に焦点を当てた製品開発ができます。
「経済成長」の面を見てみると、「薄利多売」は利益の残らない自転車操業に陥りがちなのに対して、「厚利少売」は高利益率による継続的な成長が望めます。
「競争」に関しては、「薄利多売」が競争の激しい市場で差別化の少ない価格提案となる一方で、「厚利少売」は競争の少ない市場で独自の価値提案が行えます。
「製品差別化」の側面では、「薄利多売」が標準化されて製品を提供するのに対して、「厚利少売」は独自性・高価値の提供が行えます。
最後の「認知」の点では、「薄利多売」が広告依存のビジネスになりがちで、常に集客を必要とするのに対して、「厚利少売」は高い顧客満足度により、顧客がSNSや口コミを通じて次の顧客に広げてくれる可能性があります。
いわゆる「レッドオーシャン」と「ブルーオーシャン」の対比となっており、これを見て「薄利多売」型のビジネスを始めたいと思う人はいないでしょう。それなのに現実は「薄利多売」の人が多い。それはなぜかと著者は語ります。
薄利多売になってしまうパターンのひとつは、とにかく儲けたくてビジネスを始めてしまい、場当たり的に施策を重ねているうちに薄利多売に陥ってしまうものです。
もうひとつは、とにかくつくりたくてビジネスを始めてしまうケース。自分の手がけた製品の良さを信じるあまりに市場調査が不足して売れ残り商品が増えてしまい、結果として薄利多売に陥ってしまうというものです。
そのような状態に陥る前に、3つのステップを回して厚利少売を目指すべきだというのが、本書の主張です。
第1ステップ 「価格を上げる」
第2ステップ 「お客さんを減らす」
第3ステップ 「高い価値を提供する」
最初に、背伸びでもいいので単価を上げます。いくらまで上げるかは、第3章の「成功からの逆算」で決めます。
次に、価格を上げたことにより目標利益を達成するための販売量が減ります。サービスであればユーザー数を減らすことができます。
そうしてお客さんの数が減れば、コストや時間といったリソースも減らせるので、利益が多く残ることになります。そのお金は、価値を感じてくれているお客さんのために使います。サービスや製品の品質向上、サポートの充実などにより、競合との差別化がより明確になります。これにより、サービスや製品がより強固になります。
この3つのステップをPDCAサイクルのようにくるくる回し、厚利少売ビジネスをどんどん強化していくわけです。
著者はここで、厚利少売ビジネスの邪魔をしているものの正体を明かしてくれます。これまでに著者が経験した、数え切れないほどの経営者からの相談によって見えてきたものです。
それは、「厚利少売の実現をもっとも邪魔するのは思考(マインド)である」ということです。
著者に相談する経営者を分析すると、厚利少売に踏み切ることに際して、「やり方がわからない」という人よりも「勇気がありません」「背中を押してください」という人のほうが圧倒的に多いそうです。第2ステップの「お客さんを減らす」という部分に恐怖してしまい、頭では利益のほうが大事とわかっていても、つい「売上が多いことが正義」と思ってしまうのです。
ただ、これは見方を変えれば「勇気さえあれば厚利少売ビジネスは誰にでもできる」ということでもあります。必要なのは本人の覚悟と行動だけなのですから。
著者は「日本はすでに沈没している」と言います。本メルマガの冒頭挨拶に示した数字は、本書から引用したものです。
先進国の中でただ1国、1人あたりGDPが増加していない日本は、世界の中で新たな付加価値を追加できていない国であることの証明です。このままいけば、やがて日本国民は生活に必要なものが「高くて買えない」という状態になるでしょう。
しかしながら、それはすべての日本人が貧しくなることを意味しません。買えない人と買える人の二極化が激しくなるだけです。ならば買える人に高く買ってもらい、自分も買える人になればいい。それが日本中に広がれば、日本のGDPは上がるはず。それが著者の主張です。横並びの「薄利多売」はもうやめようということです。
さて、ここからが本文です。第1章では、厚利少売で必要な4つの基本原則が解説されています。
(1)提供する価値に責任をもつ
(2)供給量をしぼる
(3)「売上脳」ではなく「利益脳」
(4)異常値になる
(2)と(3)については何となく想像がつくかと思いますので、(1)と(4)について触れていきましょう。
(1)は本書の本文の最初の部分なのですが、なかなかに濃厚です。お客さんが提供される商品やサービスにどのような価値を感じて満足するかが述べられています。それを理解した上で、自分の提供する価値に責任をもつことが大事だというわけです。
例として高級ブランドの価値が挙げられています。
(1)自身が経済的に成功している、あるいは一定の社会的地位にいることを示せる
(2)製品の品質や耐久性が高く、1つのアイテムを長く使える
(3)限定品や特別なコレクションは、独自性や希少価値がある
(4)ブランドの背景にある物語・歴史に共感している
(5)デザインや芸術性が高く、アート作品としての魅力がある
(6)購入価格よりも高く再販されることもある(=投資対効果が大きい)
(7)高級ブティックでの購入体験や専用のカスタマーサービスに満足感を得られる
これらの価値に満足するからこそ、高級ブランドを訪れる顧客はリピーターになるわけです。自社が顧客にどのような価値を提供できるか、それは顧客に満足してもらえるものなのか。この見極めを続けることが厚利少売の基本になります。
(4)の「異常値になる」は、普通ではない、競合がやっていないことをやることです。厚利少売においては、100万人に知ってもらうのではなく、100人に絶対に必要だと思ってもらう必要があります。
厚利少売ビジネスでは全員にいい顔はできないし、する必要もありません。でも自分たちが提供する製品やサービスを好きになってくれた人がいたら、その人には最善を尽くし、もっと好きになってもらわなければなりません。その覚悟が厚利少売ビジネスには欠かせません。
まだ第1章を終えたところですが、本書の雰囲気を感じていただけるかと思います。以下の内容は、目次で想像していただき、気になったら本書を読んでみてください。