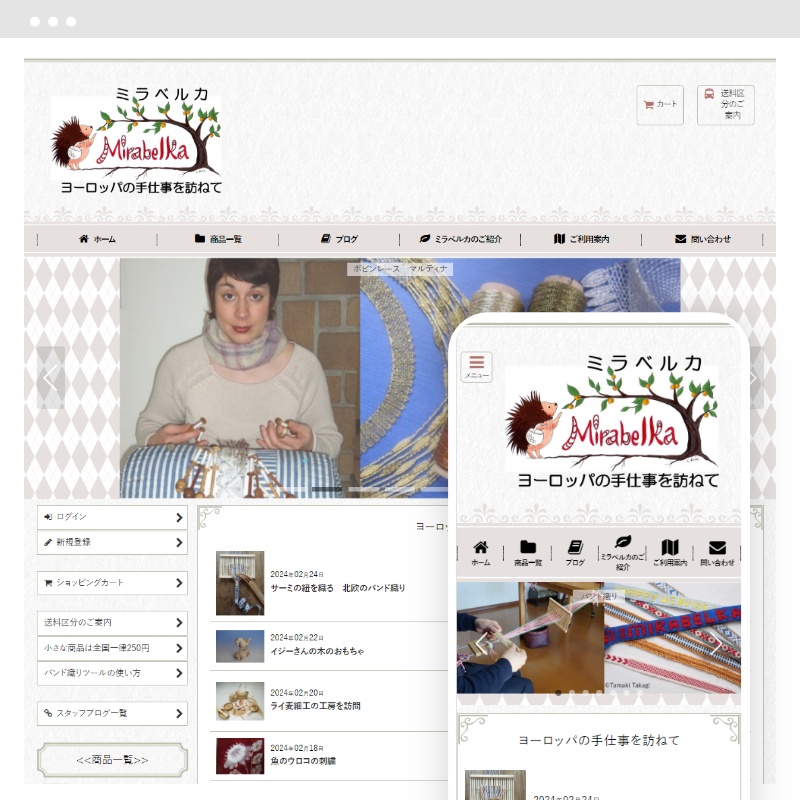
皆さんは何か「手作り」されていますか?
まず「手作り」というとどんなものを思い浮かべられるでしょうか?
私は手料理を作るのが好きですし、自分で手縫いした風呂敷バッグや革のキーホルダーを愛用していますし、木工DIYで椅子や家具を作ったりもします。
ホント、自分で楽しむだけなので精度も見栄えもイマイチですが、自己満足度だけは高いのです(^^;)
世間一般で手作りといえば、お料理、手芸、手編み、手縫い、工芸、工作、陶芸、日曜大工……。
総称すると「ハンドメイド」や「DIY」、「クラフト」などと呼ばれるものはたくさんありますが、一般的には大きな工場や電機や機械設備で規格品を大量生産するのではなく、人が手と簡単な工具や道具を使って1つずつコツコツと作っていくイメージの物ですね。
21世紀の今、先端技術を使った電子工学やIT,バイオ、AIなどのいわゆるハイテク工業全盛の時代の中で、超アナログで超ローテクな手作りやハンドメイドの市場は成長市場で、ハンドメイド作品の売買市場も増えてきていますし、さまざまな種類のハンドメイドのノウハウや技術を教える教室やセミナー、ハンドメイドするための道具や工具、資材、材料の市場も大きく広がっています。
便利さや機能、精度、均一な品質、性能の良さ、コストパフォーマンスだけが商品の価値ならば、すべてがハイテク工業製品でいいじゃん! となってしまいそうですが……。
なぜだか人間という生き物は、機能、性能、利便性、コスパ以外の手間をかける労力や過程など、アナログな不便さや時間を費やすことにも「付加価値」を感じたり、製作者の「思いや真心」という物理的には存在しないはずのものを感じて重んじる習性を持っているようですね。
例えば……。
私の7歳の誕生日には母が手編みのセーターをプレゼントしてくれて、夕食には私の大好物のハンバーグとケーキを出してくれた。
↓↓↓↓↓ が実は… ↓↓↓↓↓
私の7歳の誕生日には母が既製品のセーターをプレゼントしてくれて、夕食には私の大好物の冷凍ハンバーグとコンビニのケーキを出してくれた。
では 印象が全然異なりますよね。
セーター、ハンバーグ、ケーキの品質や機能、性能、味はほとんど同じかひょっとすると既製品、量産品の方が良いかも知れませんが、それが子供の目の前に出てくるまでの母の手間暇や思いを考えると、その価値はまったく違ったものになります(感じます)よね。
「手作り」には、このように「事実や実態」を超えた魔法やファンタジーのような魅力や価値がきっとあるのでしょうし、それに気づいて惹かれる人がハマっていくのでしょう。
さて今回のお店は…2020年6月以来、2度目の登場の「ミラベルカ」さんです。
ミラベルカさんは 店主ご夫婦の娘さんがチェコの方と結婚され、現地に在住されていることをきっかけに、チェコの手作りクラフト品を販売するお店として始められたお店でした。
現在もチェコの品も扱っておられますが、「チェコ」という軸とは別に「ハンドメイドクラフト」という軸で、新たなご縁でチェコ以外の新たな商品にも注力され、徐々に売れてきているようです。
それでは「ダメ出し!道場」始まりです!
第一印象:手づくりをテーマにしたお店!?

トップページ看板画像の「手づくりのある暮らしを訪ねて」と、上部スライドショー画像のいろいろな外国人の職人さんらしき方々の物を作っている写真や、その下のトピックスの見出しから、なんとなく海外の職人さん達のハンドメイド商品を販売しているお店かな…というところまではなんとなく感じられます。
ただ、トップページ上部だけ見ても、とくに国名や地名も見当たらず、またどんな運営者がどんな思いやコンセプトで運営しているお店なのかも、すぐには伝わってきません。
かろうじて、ヘッダーの <title> 部分に気づいた人には、「東欧のクラフトネットショップ」だと分かるのですが、スマホユーザーにはそれも見えません。
正直、「何屋さんなのか」が漠然としていてなかなか分かりません。
メニューのプロフィールページを拝見すると、
2005年に創設、手づくりのある暮らしを訪ねて素敵だなと思うクリエーターとコンタクトを取り、彼らの作品をミラベルカで紹介していること、チェコや北欧、東欧諸国の職人・クラフトマンの手作り作品の紹介をしていることなどが分かってくるのですが……。
この辺りの概要は出来ればトップページに来店して数十秒以内に伝えられると良いでしょう。
初見・初来店の方が「何の店?」「どんな店?」「どんな店主がどんな思いで、どこでいつからやってるの?」「何が強み?」「何が得意?」「何が出来るの?」
それらが短時間にパッとわかるトップページになっているか? を意識して見直していきましょう。
インタビューで浮き彫りになったこと

4年前にもインタビューしているので私は概要を知っていたのですが、あらためてご紹介します。
お店は千葉県船橋市に在住の野中ご夫妻で運営されています。ご夫婦ともに千葉大学で工業デザインを学び、それぞれメーカーの開発部や百貨店や商品研究所などで商品・製品開発を経験された後、一緒に会社を設立。商品開発と貿易業務とミラベルカの運営をなさっておられます。
ミラベルカのきっかけは、娘さんがドイツ留学中に出会ったチェコ人の男性との結婚を機にチェコとご縁ができて、現地を訪れるようになり、チェコのナチュラルでスローなライフスタイルを通じて、現地の生活の中に根付いた木や、植物など自然素材を用いた手仕事のクラフト(工芸品)にすっかり魅了されたことです。
一つずつ手仕事・ハンドメイドで時間をかけて作られた商品が、日用品としてリーズナブルな値段で販売され、購入され、人々の生活の中で使われている。
そうした環境やライフスタイルも含めて、チェコのクラフトを日本に伝えて懸け橋になりたいと考えられたのが最初。
ただ、ここ数年の間に、日本国内でのイベントで出会った日本人の作家の方が、北欧の先住民サーミ族の織物「バンド織」を日本に初めて伝えた専門家・研究家で、その方と仲良くなり、バンド織の指導を受け交流する中で、バンド織の織機の改良について相談を受け、商品開発の経験豊富な野中(夫)さんが試行錯誤し、新たなバンド織機を開発したそうです。
その作家先生の活動も通じて、バンド織りツール類が売れてきているとのことです。
バンド織りは北欧のものでチェコとは無関係ですが、新たな軸として期待、注力したいとのこと。
具体的なダメ出し&改善策

初見、初心者の目線でミラベルカさんを見ていくと、ハンドメイドの作品・完成品はそつなく商品説明されていて、ストーリーも分かりやすく、好みさえ合えば「モノ」として買いやすいページになっていると思うのですが…
ハンドメイドツールの方は、既にやっていてよく知っている方には買いやすくても、知ったばかりで興味は持った程度の方には、
やってみたい!→やってみよう!→買おう!
と思えるほど分かりやすい魅力を感じるコンテンツがありません。
例えば バンド織りでも…
https://mirabelka.ocnk.net/product-list/134
カテゴリーページに1本の動画こそあれ…
たとえば、へドルやシャトルの違いで作品の何が変わるのか?
どんなときにどの道具を選ぶのか? など概要すら分かりません。
せめて教則本やノウハウDVDなど教材が商品として用意されていれば、始めてみようかという気にもなれますが…
現状のコンテンツだけではミラベルカで初めてバンド織を知っただけの人にはハードルが高過ぎます。
むしろ、作家先生の講座や外部のサイトや本などである程度知った方が買いに来ているのなら、おちゃのこミラベルカ内だけでもそのレベルまで「バンド織りとは?」を知ることができるだけのコンテンツを用意するべきでしょう。
------------------------------
また、例えば ボビンレースのボビンのページ
https://mirabelka.ocnk.net/product-list/30
ボビンを製造している動画はありますが…
肝心のボビンレース手芸をやって作品を作っているコンテンツはありません。上級者には有効でも初心者には「?」です。
料理の初心者に、包丁を鍛造しているシーンを見せているのに、肝心の野菜や果物を切っている切れ味や使い勝手を見せるシーンがないようなものです。
道具屋さんはつい、道具のスペックばかり説明してしまいがちですが、それはプロを相手にする時には有効でも、初心者を相手にするときは敷居を高めて逆効果(難しくてできないと思わせる)。
初心者にはスペックより、まず「何ができるのか?」「どんな使いこなし方や魅力があるのか?」を実演して理解させることが必要です。すると、
「私もそんな風にやってみたい! できるようになりたい!」
から↓↓↓↓↓
「それ欲しい! 買いたい!」になるのです。
例えば木工初心者に対して、
「このノコギリはハイカーボン鋼材で刃の長さ300mmで厚み0.5mmで刃の数が何百個で…」とスペックを説明しても、初心者には魅力を感じられませんが、
「このノコギリを使えば木材をこんなに滑らかに真っすぐ簡単に30秒で切ることができます。滑らかに切った木材で椅子を作れば、触り心地、座り心地のよい椅子が作れますよ!」
と実演して見せる方がはるかに魅力を感じ、「やってみたい! 欲しい! 買いたい!」につながります。
ミラベルカさんで販売しているハンドメイドの道具類全般に関して、こうした実演、使い方、できあがる作品事例を、ぜひ動画を含めて分かりやすく魅力的なコンテンツで用意していきましょう。
総評
従来、「チェコの」手づくり商品という軸だったミラベルカさんに、「手づくり(ハンドメイドクラフト)」という軸でチェコ以外の国や文化の商品の軸ができたことで、今後のビジネスの展開の可能性も広がったように思います。
まずは「バンド織り」関連の 商品化、パッケージ化をハードだけでなく、ソフト(教材や教室など)も含めて作家先生とコラボして広げられれば、ポテンシャルは大きいと思います。
またそれをモデルケースに、他のクラフト(ペグルームやボビンレースなど)のツール類も、手法・ノウハウの教材化や講座化ができれば、小中学校やフリースクール、専門学校や障碍者の就労支援施設などに講座+ツール として営業・販売の可能性も出てくると思います。
フリーランスや在宅ワーカーのクラフト作家さん、ハンドメイドが趣味という方々も、より始めやすくなると思います。
------------------------------
これを機会に、完成品・作品販売 のコーナーとツールの紹介・販売のコーナーを分かりやすく分けられてはいかがでしょうか?
オロビネツ(蒲)のバスケットとか木のおもちゃとかライ麦細工などはあくまで完成品の作品販売だけで、作るための道具や材料やノウハウを売っているわけではないので…
お客様の導線を「ハンドメイドを作りたい人」と「作品を買いたい人」に分かりやすく分ける方がお店の特徴や魅力も伝わりやすくなると思います。
------------------------------
最後にブログやSNS活用について。
Instagram、X、Facebook、exciteブログをやっておられますが、
Instagram→3年間更新なし
X→3年間更新なし
Facebook→1年間更新なし
exciteブログ →8か月ぶりに更新
とほぼ情報発信がなされていません。
同じ内容でも構いませんので、それぞれにショート動画を使ってバンド織りやペグルームなどの実演風景から作品事例を紹介するコンテンツを発信していきましょう。
ミラベルカのハンドメイドツールを使ったヨーロッパ各地のハンドメイドは楽しいですよー! 学校や高齢者・障害者施設や子供達にも始めやすいですよー! といった啓蒙活動で潜在需要を発掘できれば、まだまだポテンシャルは大きいように思います。
以上。「ダメ出し!道場」でした!

私たちはネットショップミラベルカを2005年に創設以来、手づくりのある暮らしを訪ねて出会いの旅を続けています。そして私たちが素敵だなと思うクリエーターとコンタクトを取り、彼らの作品をミラベルカで紹介しています。
チェコのボビンレース、北欧サーミのバンド織、ペグルーム(棒織機)など手芸道具、また、木のおもちゃ、ボビンレースや蒲やライ麦製品、刺繍など、東欧諸国の職人の手作り作品も扱っています。
言葉を超えた手仕事の交流が、国や人との懸け橋になることを願ってブログも書いています。
https://mirabelka.exblog.jp/
これからも、細く長く続けていけたらと思っています。こんなネットショップですが、売り上げは少しずつ伸びています。ただ、ブログやHP、ネットショップ(おちゃのこ、ヤフー)と情報が分散していましたので、おちゃのこを中心に情報を整理しました(つもりです)。
お客様に伝わりやすいおちゃのこになっているかどうか、チェックしていただければと思い応募しました。